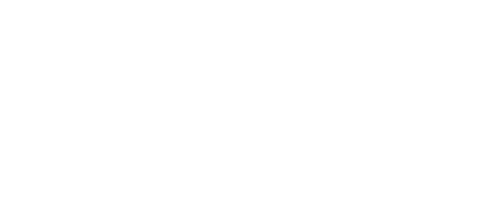
ここ最近、家庭でも無線LANを使う家も出てきて、無線LANというものが一般的になってきている。「無線LAN」とは文字通り「無線」+「LAN」である。「LAN」はLocal Area Networkの略であり、たとえば企業内や家庭内の小さな領域において、複数のコンピュータ間でファイルのやりとりをしたり、インターネットへの橋渡しを行うものである。これはコンピュータが家庭に複数台ある状況が出てきたことやADSL、FTTHなどの登場により一般化している。しかし通常は、Ethernetケーブルを用い、通信をする。一般に10BASE-Tでは10Mbps、100BASE-Tでは100Mbps通信速度(最適値)で実現する。ではどうして無線なのか?、線が無いのにどうして通信が出来るのか。こういったところに最新技術が使われている。こういったところに注目して無線LANはいったいどういうものかということを考えたい。
無線LANを論じる前にネットワークについて解説をしておく。後の無線LANの解説で説明を簡単にするためのものである。ネットワークは7層からなる階層構造をとっている。これは、階層構造にすることにより、上位の層では、下位の層を意識しないので、ソフトウエアのプログラミング等で、より容易になる。以下に7層の階層を示す。
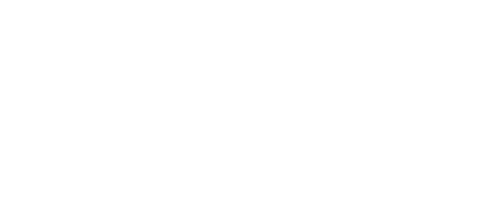
アプリケーション層は、転送されてきたデータをどうするかという事を行う。プレゼンテーション層は文字コードなど表現形式の違いを埋めるものである。セッション層はどうやって接続するかといった事を受け持つ層である。ここでは、データの授受や同期の制御を行う。ネットワークはデータをより小さなパケットに分けるので、トランスポート層は、誤り制御やパケットが順番通りにきているのかチェックする事を受け持つ。代表的なプロトコルにTCPやUDPがあげられる。ネットワーク層では主に相手先のアドレス(IPアドレス)を付加し、これをホスト(コンピュータ)の住所とする。ネットワーク上のデータはこのIPアドレスでネットワーク上をバケツリレーの様に送っている。データリンク層では、相手との間にデータリンクという論理的な経路を張り、ビット誤りなどを検出し、1対1のコンピュータ間の転送を保証する。この層はMAC層とLLC層の2つにさらに分かれる。一番下位の物理層では、RS−232C(シリアル)、やEthernet(10BASE-Tや100BASEーTXなど)の物理的、電気的な接続を保証するものである。たとえばこの線はグラウンドといった具合である。
2.1でネットワークがどうなっているのかだいたい見当がついたと思う。では無線LANと有線LANのどこが違うのだろうか。それは物理層とデータリンク層である。ネットワーク層より上は、下の層で下位の層を意識する事はない。これは転送する媒体が変わるのだが、物理層とデータリンク層で、有線と無線の差を吸収することが出来るのである。では無線LANの物理層や、データリンク層はどうなっているのか。
2.1.1 データリンク層
データリンク層はどこが違うのか。データリンク層のMAC層が無線LANと違う。
有線LANの場合
データリンク層は、1対1のコンピュータ間の通信を保証するものである。有線LANでは、この1対1のコンピュータには、ケーブルがついているこれならお互いのデータの衝突を検出できる。このため有線LANではCSMA/CD(Carrier
Sense Multiple Access with Collision
Detection)方式という方式が主に使われている。この方式は早い者勝ちで、転送路(ケーブル)へのデータ送出権を獲得する方式である。もし複数のコンピュータが同時に転送路に送出した場合(データの衝突がある場合)、一定時間待ってから同じデータを出力する。この待ち時間をランダムに設定する事で再衝突の確率を下げている。CSMA/CD方式以外にも、データの送出権をつながっているコンピュータ間で巡回するトークンパック方式も存在する。
無線LANの場合
無線LANはケーブルなしで、(たとえば電波に乗せて(詳しくは後述))データを送り出さなければならない。つまり無線LANではデータの衝突を検出することが出来ない。空間に送り出す訳なので、受信しない限りデータが空間上にあるかどうかはわからないからである。このため無線LANでは、CSMA/CA(Carrier
Sense Multiple Access with Collision
Avoidance)という方式がとられている。これは、まず送信の前に、ほかのコンピュータ間で通信が行われていないかを調べ、さらに、自分宛のデータ(パケット)が送信されていないかを調べる。その結果衝突が起きないと判断された場合、送信を開始する。もし衝突が起きると判断された場合CSMA/CD方式と同じやり方で、送信を待つ。今回は衝突が感知できないため、複数のコンピュータ間で同時に送信をはじめ衝突が起きる場合があり得る。このためこの理由で衝突が起きた場合はMAC層より上の層で誤り検出、訂正を行う。
2.2.2物理層
物理層は有線LANと大きく違う。無線の種類(電波、赤外線、レーザーなど)によっても物理層は違ってくる。また無線だけでもいくつかの変調(電波をどうやって電気信号に変えるか)の問題もある。これについては後述の無線LANの種類についてで述べる。
無線LANといってもいろいろな方式が存在する。ケーブルが無ければ無線LANになるので、電波、赤外線、レーザーといった様々な方式が存在する。ここでは無線LANにはどういった方式が存在するのか説明していく。
2.3.1 電波方式
免許不要な周波数帯の電波を使用し(規格によって異なる無線LANの規格で後述)MAC層、物理層が無線LAN専用の方式(MAC層については先述)を用い、現在最大54Mbps(理論値)を実現する方式。一般に無線LANというとこの方式を指す。この方式では物理層で、電波を電気信号に変える必要がある。電波方式では主にスペクトラム拡散通信方式(元々は軍事用)を採用し、ノイズに強い通信方式が採用されている。製品構成は、無線LANアダプターと有線LANとの橋渡しをするアクセスポイント、またビル間を通信するビル間通信ユニットがある。
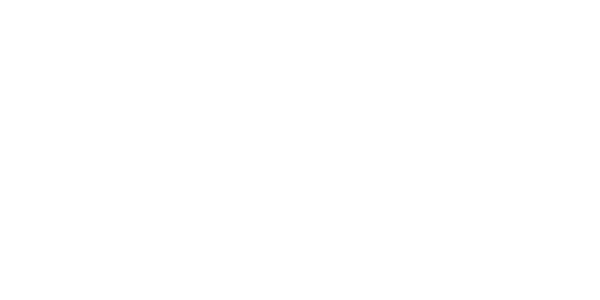
スペクトラム拡散(Spread Spectrum)通信方式
電波を用いる無線LANでは主に位相を使ってデジタル信号を電波に乗せている。デジタル信号を電波に乗せる事を変調と呼ぶ。しかし、一般的に無線では特定の周波数(たとえば東京ではラジオのNHK第1は590kHz、フジテレビの映像は映像193.25MHz、音声197.75MHzなど)の1波を使って通信を行っているが、この周波数にノイズがあると通信できなくなる。また、ラジオの選局などで苦労したことがあると思う。
スペクトラム拡散通信方式(以下SSとする)とは、広い幅の周波数を同時に使って通信行う方式のため、もし特定の周波数にノイズがあってもほかの周波数ではじゃまされないためノイズに強いとされる。元々は軍事用の秘密通信方式から発展し、現在一般に知られているものとしてGPS(Global
Positioning System)がある。またSSは、大きく2つに分かれる。
DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)
DSSS方式は、直接拡散方式と呼ばれ、BPSKという位相変調をしたあとPNコードと呼ばれる特殊な拡散符号を掛ける事により、周波数スペクトラムを広帯域に拡散して送信する方式である。
FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)
FHSS方式は周波数ホッピング方式と呼ばれる。スペクトラム拡散方式のうち4FSKまたはBPSKという位相変調したあと搬送周波数を拡散符号から出来るホッピングパターンに沿って切り替えることにより、広帯域信号に拡散して送信する方法である。帯域を複数のチャンネルとして使えるため、同時に複数のコンピュータ間で通信が可能で消費電力が押さえられる特徴を持っている。
2.3.2 電波置き換え方式
前述の無線方式と同様に電波方式と同じ周波数の電波を利用して1〜2Mbps程度のの転送スピードのものですが、MAC層、物理層は有線LANで使うもの(IEEE802.3規格化されている)つまりMAC層ではCSMA/CD方式を用い、ケーブルの部分だけを無線に置き換えるものである。
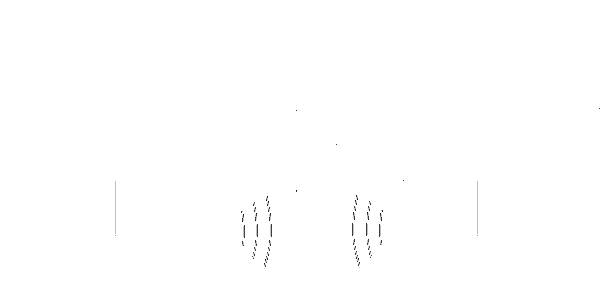
2.3.3 赤外線方式
無線は、電波だけではない。一般に無線LANとは別のものとされるが赤外線でも良いはずである。赤外線方式は有線LANで用いられているもの先にメディア変換アダプタ(電気信号を赤外線に変える)をつなぎ光無線HUB(アクセスポイント)と通信するものである。赤外線方式は直射光または反射光が届かなければならないこと、転送距離が10m以下という短所があるがこれをクリアできれば10Mbps程度の通信が出来る。
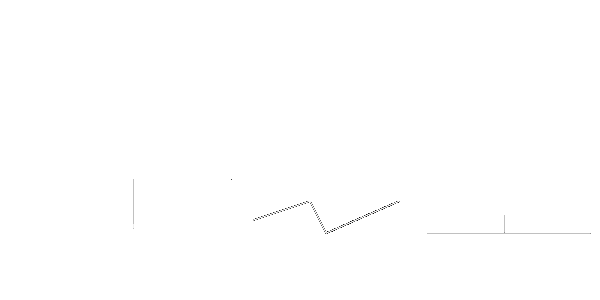
2.3.4 IrDA赤外線方式
よくノートパソコンやPDAなどに下の図の様なテレビのリモコンの先の部分のようなものを見たことあるだろうか。これがIrDAポートである。IrDAは赤外線でデータ通信していたのである。こちらは専用のアプリケーションとこのポートを用いることにやって4Mbpsで通信できる。
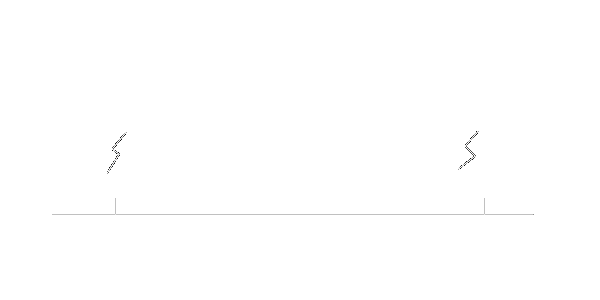
2.3.5 レーザー方式
レーザーでも通信できる。レーザー光は直視すると失明するおそれもあるため危険であるが、たとえばビル間通信などで、有線LANにレーザー通信装置をつけて、有線LAN同士をつなぐものである。
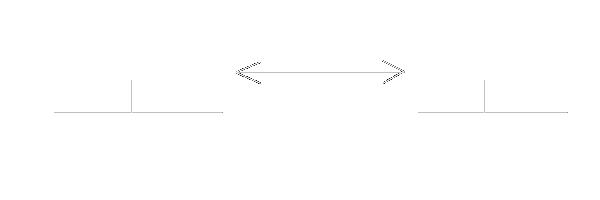
無線LAN(電波方式のもの)はIEEE 802.11で規格化されているが転送速度や送出周波数の違いで規格が異なる。出てきて新しいもののため有線LANと比較して多くの規格が乱立している。審議中のものも含めて、以下に示す。
3.1
IEEE802.11
2.4GHz帯を利用し、これまで説明してきたCSMA/CAやDSSSやFHSSを利用して、無線LANを構築する規格。転送速度は2Mbps(理論値)である。以下の規格のベースとなる規格である。
3.2
IEEE802.11a
IEEE802.11をベースに、無線通信の周波数を5.2GHz帯を利用することによってスピードを54Mbps(理論値)まであげることに成功した規格。しかし、別の周波数帯域を使用したことによりIEEE802.11や802.11bなどとは互換性を失ってしまった。また電波法の関係で、室内でしか通信を行えない。(5.2GHz帯が航空無線、衛星や気象レーダー等と同じ周波数帯を使うため干渉のおそれがあり非常事態を招くおそれがあるため室外での利用は禁止されている。詳しくは後述)
3.3
IEEE802.11b
これもIEEE802.11をベースに無線の周波数をIEEE802.11と同じ2.4Ghz帯を利用しスピードを11Mbps(理論値)にまであげる事に成功した規格。基本的にはIEEE802.11と互換性を持つ。この規格の方がIEEE802.11aよりも先に実用化している。
3.4
IEEE802.11g
これもIEEE802.11bをさらに拡張し、54Mbps(理論値)を達成した規格。IEEE802.11aで用いられたOFDMと特殊なPBCCという特殊な符号化を行うことにより、スピードアップを可能にした。ただし、利用する周波数はIEEE802.11bと同じ2.4GHz帯なので互換性は確保されているが現状ではIEEE802.11bとIEEE802.11gでの通信を1つのチップで可能にすることは難しいため、どちらかを選択するといった感じになる。
3.5
IEEE802.11h
IEEE802.11aをベースとし、5.2GHz帯を用い、転送速度は54Mbps(理論値)と変わらない。しかし、自動的に混信の無いチャネルを選択する機能や送信出力を最小限にまで絞り込む機能を搭載したことにより実際の転送速度を上げるというねらいがある。ただいま策定中である。
3.6
IEEE802.11e
IEEE802.11/11a/11b/11gに帯域制御機構を搭載したもの。これはユーザ認証やアクセス制限を提供するセキュリティ機能やQoSというマルチメディアデータを意識したサービス品質向上技術を搭載している。またこの規格はこの機能を実現するためにMAC層のアクセス制御がDynamic
TDMA方式という短時間ずつ交代して通信を行う方式が採用されている。これはコンピュータ間で制御情報を交換して、転送するデータに優先順位を決めることによりより効率的なデータ送受信を可能にするねらいがある。この規格も策定中で、まもなく確定予定である。
3.7
IEEE802.11i
IEEE802.11/11a/11b/11gにセキュリティ・認証機能を付加したもの。MACアドレスによる制御やWEP(4.2で後述)では心許ないので、TKIP(Temporary
Key Integrity Protocol)をWEPに追加し、暗号化方式に今までののものよりも強力なAES(Advanced
Encryption
Standard)を搭載しより強いセキュリティを実現する規格である。AESはアメリカ国防省がDES暗号に変わる新暗号を募集し、128、192、256bitの3種類から選べ、鍵をブロック化して違った方式で暗号化する方法で速度と暗号強度を上げている。これは2003年上半期には規格が確定する模様である。
4.無線LANの利点・欠点
ここでは無線LANの利点・欠点について述べたいと思う。
4.1 無線LANの利点
a.ケーブルがいらないので配線スペースが不要
有線LANだとオフィスなどでPC等を置く場所を変更するとそのたびにケーブルを張り直さなければならないので大変である。またPCの裏側には、ディスプレイやUSB、キーボード、マウスなどたくさんのケーブルがあるので「ただでさえケーブルでいっぱいなのにLANケーブルもだなんて勘弁してほしい。」といった人にはお勧めしたい。
b.端末の設置や移動が自由
特にノートパソコンを使っている場合など、家の中ではどこでも使いたいといった考えをお持ちの方も多くはないだろう。そうなると無線の方が、ケーブルが無いのでそこでも使うにはとても都合が良い。
c.移動体での利用が可能
電波の届く範囲なら移動していても通信は可能である。しかし、電波出力が大きくないので携帯電話の様な使い方は無理である。しかし、工場内を動くロボットや工場のような大きなところでの自転車での移動であれば十分利用できる。またちょっと話変わってくるが無線LANの設備があれば電車の中など大きな空間の中でも使用が出来る。ただし、車外との通信は通信衛星など無線LANと違う媒体での転送が必要だ。
d.迅速なLANの構築が可能
ある時期だけネットワークが必要になる場合(たとえば展覧会など)には設備の設置等も簡単なので便利である。
e.屋外通信が可能
道路等があり、オフィスが別の場所にあったとしても遠くなければ(数メートルから数十メートル)、ビル間通信ユニットを設置するだけでネットワークが組める。専用線を引くと、回線使用料など維持費がかなりかさむが、無線LANなら、設備の保守と電気代だけなので安く押さえられるという利点がある。
4.2 無線LANの欠点
a.有線LANと比較すると転送速度が遅い。
無線LANは現在の通信速度は最大で54Mbpsである。しかし、有線LANで一般的に使用されているものは100Mbps(100BASE-TX)〜1Gbps(1000BASE-T)であるため速度の点から考えると有線LANに分がある。またCSMA/CD方式の特性上、アクセスポイントにアクセスする端末数が増えると、処理速度が極端に低下する。IEEE802.11bを使っている場合には、LAN側の実効速度が4〜5Mbpsなので、12MbpsのADSLやFTTH(ex..Bflets)等の場合帯域をうまく使い切れない場合がある。(実際Bfletsの10MBに契約している家の実効速度は6Mbps前後である。)
b.盗聴やデータ改ざん等セキュリティ上の問題がある。
もし、ビルで使っていたりすると、当然の事ながら、電波がビルの外へ漏れる。そうなると、悪意のある者が、その電波を傍受し、データを書き換えてしまうという事が十分に考えられる。これに対するセキュリティとして、MACアドレスに対する制限やWEPという128bitの暗号に変換してから送るという事が出来るが、公共の場所ではMACアドレスの制限は出来ない。またこれはアクセスポイントが使えないだけなので、電波の方を傍受することは可能なので実質、盗聴防止にはWEPだけとなってしまう。WEPは128bitなので2の128乗通りの鍵のパターンがあるが、グリットコンピューテイングなどで、128bitの公開鍵を解読した等、現在解読できない鍵は無いので、機密情報などを扱うには注意が必要である。また、WEPを使う転送速度が落ちることも報告されており、転送速度を上げるためにWEPを使わないで転送している事もあるらしく、この場合は傍受出来れば、データは筒抜けになってしまう。無線LANが一般化するには、もっと強い暗号が必要になると考えられる。IEEE802.11hの登場が待たれる。
c.有線LANと比較すると高コストである。
有線LAN(100BASE-TX)のLANカードと無線LANのLANカードを比較すると、有線LANのがかなり安い。また無線LANのアクセスポイントと有線LANのハブ(3台以上のコンピュータをつなぐ物)を比較してもハブの方が安い。安くLAN環境を手に入れようと思っている人には、無線LANは向かない。
d.ほかの電化製品(電子レンジ)やbluetooth、医療機器などと電波が干渉する。
一般的に使われている電波方式の無線LANでは電波を使ってデータを放出するので無線LAN以外の電波と干渉することが知られている。電波法で、2.4MHz帯、及び5.2MHz帯はほかの様々の製品でも使えるようになっている。代表的な干渉物はbluetooth、電子レンジ、医療機器、航空無線である。このうち前の2つは2.4GHz帯で、あとの2つは5.2GHz帯で通信を行っている。もし電波が干渉するとお互いのデータが壊れることになってしまうので、通信速度が極端に低下したり、ひどいときは通信できなくなってしまう。(bluetoothはチャンネル1MHzごとに79chを持っており、1秒間に1600回チャンネルの切り替えを行いながら通信するので電子レンジや無線LAN側から受ける影響は小さいが、逆にbluetooth側から無線LAN側に与える影響は大きい。こういった例外もあるが通常は双方影響を受ける。)具体的に電子レンジの前でIEEE892.11bの無線LANを使うと、極端に通信速度が低下することも報告されている。2.4GHz帯の方は、生命に関わることは大きくないといえるが、5.2GHz帯の方はどうだろうか。こちらは航空無線や、医療機器である。電波の干渉により、通信できなくなると、生命の危険に直結する可能性が大きい。そこで電波法では、5.2GHz帯を使う無線LANは屋内のみの使用に限るという規制が施されている。家で介護を必要としている人や、心臓ペースメーカーをしている人がいたら注意が必要である。(無線LANは使わない方が良い)
5.終わりに
今回無線LANを調べるあたり、その比較対象に有線LANとしていろいろと行ってきたが、利点も欠点も無線固有のものが出てきている。今後LANを構築する機会があれば有線LAN無線LANの双方の利点欠点を考えて、構築する必要がある。今後欠点は、無線LANの普及とともに克服される事も十分に考えられる。そうなると自由に持ち運び、どこでも通信が出来るという事が実現される。パソコン1台さえあればどこでもインターネットに接続できる時代がくるのは夢では無い。
6.参考資料
アライドテレシス株式会社 無線LANとは
http://www.allied-telesis.co.jp/product/musen/refer/
ZDNet JAPAN ネットランナー 2002年1月号 最強無線LANを構築する。
http://www.zdnet.co.jp/internet/runner/0201/sp3/
Soft Bank Dos'v Magazine
No.198 2002年 1月15日号 次世代標準特捜隊 no.107 IEEE802.11g
No.203 2002年 4月 1日号 特集2 54Mbps高速無線LANの実力
No.219 2002年12月 1日号 次世代標準特捜隊 no.124 IEEE802.1x
e-Words 情報・通信辞典 http://www.e-words.jp